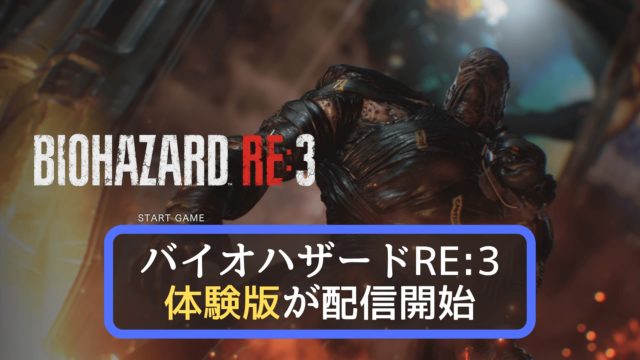こういう意見があるのは当然ですし、私もそう思います。
しかし、ネット・ゲームに関する問題は、これからの日本・世界において必ず向き合い方を考える必要があることです。それは子供に限らず大人もです。
ならどう向き合うべきか、どう世の中が変わっていけば良いかを皆さんで考える良い機会になったと思います。
皆さんもネット・ゲームとの向き合い方を見直してみましょう。
- 規制よりも教育強化を
- 大人も学べる場を
- お酒・タバコは規制せず、ネット・ゲームをなぜ規制?

規制・制限内容

オンラインゲームの使用時間制限を具体化した素案を明らかにした。使用時間の上限は18歳未満で1日60分、土日や祝日、長期休暇を含めた休日は90分とした。ただ、罰則規定などはないため、実効性は不透明だ。
(中略)
中学生以下は午後9時まで、高校生は午後10時までに使用をやめるよう求める。ただし、罰則規定は設けていないため、実質的な強制力はもたない。
条例の詳細については、日本経済新聞の記事をご覧ください。
今回の条例は18歳未満が対象とされ、時間などの制限以外にも
- 予防対策の実施
- 全国で不足している医療体制の整備
- 相談支援体制の充実
が内容に含まれていました。
私たちが考えるべきポイント
決して考え方が全て悪いとは思いません。むしろこの課題は今後の日本は深刻に向き合っていかなければならない問題です。
ですが、ネット・ゲームとの向き合い方はもっと慎重に考える必要があります。
規制よりも教育の強化を

今の時代、そして今後の未来はネットとは切っても切り離せない存在です。
仕事にも大きな活躍があります。例えば毎日通勤せず、リモートワークで仕事や会議が家で行われる時代です。
人との交流もネット・ゲームがメインになってきています。その大きな実例がSNSです。
電話も最近ではテレビ通話の方が多くなってきましたし、5Gが日本で実用化されれば、テレビ通話において人間が気づけない程の遅延となり、相手と対面で話しているのと変わらない程の快適さが予想されています。
友人との交流も実際に会わなくても済む時代になっています。
そんな時代だからこそ、ネット・ゲームの正しい向き合い方や使い方を小さな子供の時から教育していくことが大切なのではないでしょうか。
自制心を教育すべき
私はゲームが好きなのですが、一度も「ゲーム障害」とみなされる症状になったことがありません。
なぜならば、ゲームとの向き合い方が明確に決めているからです。

- ネット・ゲームを1日何時間までか
- 何時間おきに休憩を入れるのか
- 休憩の仕方は間違っていないか
ここまで自分にあったルールを決めることで私は「ゲーム障害」を回避できていると考えています。
私は他の人に比べてネット・ゲームを長時間できる人ではありません。眼精疲労や頭痛、吐き気などを感じやすい体質だからです。
だからこそネット・ゲームと慎重に向き合えています。
こういった向き合い方を子供たちにも教育する必要があります。
それは「ネット・ゲームを中断する自制心」です。
だらだらとネット・ゲームを続けてしまい結果的に長時間使用してしまうということが「ネット依存症」などを引き起こすきっかけだと考えられます。
こういった状況にならないために自分で自分を管理する意識を育てることが重要だと考えます。
ネット・ゲームの知識を教育
ネット・ゲームに対して無知でいることも病気や依存症を引き起こす原因となります。
お酒のことを知らない子供が水のようにガブガブ飲んでいたら危険ですよね。
この場合は子供にきちんとお酒そのものの知識を教えてあげる必要がありますよね。
教育者は大人全員、大人にも教育が必要
ネット・ゲームの教育者は学校の先生だけでは不十分です。
家族も子供に教育と管理が必要です。「ゲームばっかりやってないの!」という親の声も重要になってきます。
家族も教育者ということは、家族内の大人(親)もネット・ゲームについての学習が必要です。
よって、市や町での大人向けの講習会などが定期的に行われれば、子供へネット・ゲームに関する教育や管理が適切に行えるはずです。
大人も一度教育してもらう機会が必要です。
娯楽の自由を奪うなら、お酒とタバコの規制も

お酒を例に考えてみます。お酒も飲みすぎによってアルコール中毒や臓器への悪影響が分かっています。しかし、飲みすぎには規制や罰則はありません。
なぜなら飲む量とそれに影響が出る身体にはそれぞれ個人差があるからです。
たくさん飲める人もいれば、少量で苦しくなる人もいますよね。
よって、お酒の量を規制することはできません。あくまで自己管理と自己責任とされています。
ネット・ゲームも同じように考えても良いはずです。
ネット・ゲームのやりすぎは確かに心身ともに悪影響が考えられます。
「ネット依存症」「ゲーム障害」などといった深刻な問題があるからです。
しかし、この影響にも個人差が必ずあります。長時間ネット・ゲームをしていても身体に影響がない人、30分~1時間で眼精疲労や頭痛などの影響が出てしまう人もいます。
そういった個人差に対応すべき課題が「ネット・ゲームとの向き合い方」なのだと考えます。
経済的な影響
これはネット・ゲームの使用時間が規制されるということは、ゲーム・PCなどの需要自体も減らすことにもなります。
お酒で例えれば、飲酒量に規制が出来たとしたらお酒の売り上げに影響があります。それと同様なことが起きるはずです。
電子機器やゲームの売り上げが減少すれば大きな経済的影響が考えられます。
香川県の気持ちは理解できる

最近では「ゲーム障害」が話題になったので、ここを問題視することは正しいと思いました。
しかし、その対策があまり適切ではなかったように感じるものでした。
ネット・ゲームの心身に影響する問題は今後の大きな病となっていくでしょう。
ですので、これに対してどう私たちが向き合っていくべきなのかを今一度、各々で考える必要がありそうです。
ネット依存・ゲーム障害、怖いよね
以上、とろろでした。